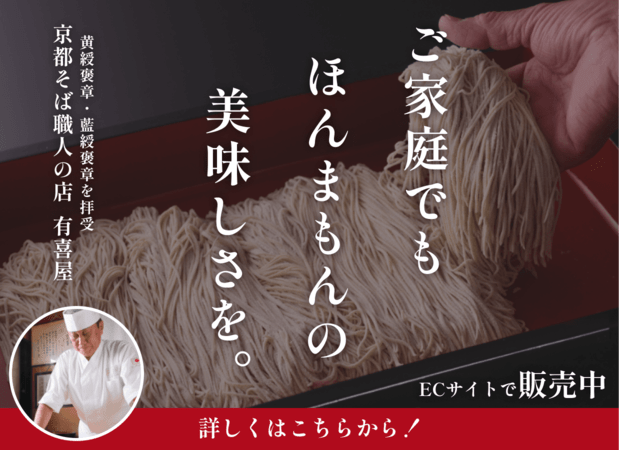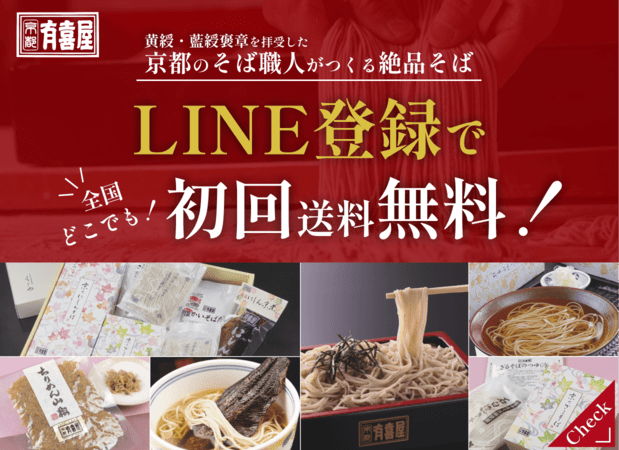COLUMN
コラム
そばの歴史と進化を解説|実はお米より前に日本に伝わった?

この記事の監修者

有喜屋 三代目店主
三嶋吉晴
有喜屋(うきや)三代目店主。有喜屋は1929年 京都先斗町に創業した本格手打ちそばと蕎麦料理を提供するそば屋です。 最年少で京都府優秀技能者表彰「京都府の現代の名工」を受彰。 手打そば職人としては全国で初となる「卓越技能章」を厚生労働大臣より受彰。 天皇陛下から授与される褒章である、「黄綬褒章」を拝受。
「そばのルーツは日本じゃないの?」
「そばはいつ日本に伝わって、いつ今の食べ方になったの?」
健康食・美容食として近年ますます人気が高まっているそばですが、そのルーツや日本での変遷について知っている人は少ないのではないでしょうか。
そこでこの記事では、そばのルーツや日本における歴史を作り方・食べ方の変遷とあわせて解説します。そばの歴史を知ることで、さらにそばに興味が湧いてくることでしょう。
目次
1. そば発祥の地は中国・チベット
そばは日本人に非常になじみ深い食べ物ですが、実はそのルーツは日本ではなく、中国の江地と呼ばれる東チベット、四川省、雲南省の境界領域という説が有力です。
そんなそばが日本に伝わったのは、旧石器時代後期といわれています。高知県内の遺跡から9300年前のそばの花粉が出土しており、埼玉県内の遺跡からは3000年前のそばの種子が発見されています。日本で稲作が始まったのは縄文時代後期の約2800年前とされているため、そばは米よりも早く日本に伝わって広がったと考えられます。
しかし、米よりも先に伝わっているのになぜそばが主食とならなかったのでしょうか。諸説ありますが、そばの殻が硬くて脱穀しづらかったのが理由と考えられています。
現在そばは「麺」の形で食べるものとして定着していますが、そばが日本に伝わって以降、長い間粒のまま粥として食べられていたようです。
2. 日本におけるそばの歴史
日本にそばが伝わって以降、初めて公的な文献にそばが登場するのは奈良時代となります。時代ごとにそばの歴史や変遷を見ていきましょう。
- 奈良時代・平安時代:非常時の食べ物
- 鎌倉時代:石臼登場
- 戦国時代~江戸時代初期:初めてそばが麺状に
- 江戸時代中・後期~:そばは庶民に人気の食べ物に
(1)奈良時代・平安時代:非常時の食べ物
そばは奈良時代の「続日本紀」に初めて登場しました。記述によると生命力が強く、日照り・水不足・寒さなどにも育つ丈夫な食べ物であったため、非常時用や緊急用の食べ物として栽培されていたようです。
当時はそばは非常食扱いだったため、貴族社会ではほぼ食べられておらず、農民が粥状にして食べていたと考えられています。
(2)鎌倉時代:石臼登場
鎌倉時代には中国から石臼が伝わったことでそばを容易に挽けるようになり、そばを食べる習慣が広がったようです。ただし、まだこの時代もそばは「麺」状ではなく、簡易的な形で食べられていたとされます。
引いたそば粉に水を混ぜて捏ねて作った餅や団子のようにして食べる「そばもち」「そばがき」、水で溶いて焼いた「そば焼き」など食べ方にも工夫が見られるようになったのも大きな変化といえるでしょう。
これ以降、そばの記述のある文献はしばらく見当たらず、次にそばが文献に登場するのは戦国時代となります。
(3)戦国時代~江戸時代初期:初めてそばが麺状に
1574年の「定勝寺文書」で初めてそばを麺状に切って食べる「そば切り」の記述が登場します。また、1706年に発刊された『風俗文選』によると、「蕎麦切といっぱ、もと信濃国本山宿より出て、普く国々にもてはやされける」とあることから、麺状の「そば切り」は信濃国(現在の長野県)の本山宿で誕生し、18世紀には既に広まっていたことがわかります。
江戸時代の初め頃は、そばは農民の食べ物ではなく、高価な食べ物として将軍や大名など身分の高いものしか食べられない高級品となっていたようです。しかし、この後、そばはさまざまな改良がなされて一気に進化していきます。
(4)江戸時代中・後期~:そばは庶民に人気の食べ物に
江戸時代中・後期は、そば文化が大きく発展した時代です。そば文化が発展したのは、水車引きの技術により大量にそばを挽けるようになったこと、そば栽培が大幅に増えたことでそばが庶民にも手の届く食べ物となったことの2つが主な理由と考えられます。
現代にも受け継がれている江戸時代に生まれた3つのそば文化について見てみましょう。
- 二八そばの登場・食べ方の進化
- 「そば前」で粋にそばを食べるのがブームに
- 「みそかそば」「年越しそば」の風習も誕生
#1:二八そばの登場・食べ方の進化
江戸時代後期に、よりそばが食べやすくなるようにそば粉につなぎを混ぜる製法が確立しました。
そば粉100%のそば(十割そば)は、そば本来の風味や味を楽しめる一方、そば打ち・調理が難しく、切れやすいという特徴があります。そのため、十割そばのみであった江戸時代初期は、そばをゆでるのではなく蒸して作っていました。しかし、そば粉につなぎを混ぜて作る二八そばが登場したことで、そば打ちもしやすくなり、徐々に茹でて提供するようになりました。
当時は醤油が高価であったことから、そばつゆは醤油ベースではなく味噌ベースで食べられていたようです。しかし、上方(京都)から醤油ベースのそばつゆが伝わると、徐々に江戸でも醤油ベースのものが主流になっていき、現代のようなスタイルとなりました。
こちらも合わせてご覧ください。
二八蕎麦の「二八」とはどういう意味?十割蕎麦との違いも紹介
#2:「そば前」で粋にそばを食べるのがブームに
江戸時代にそばがブームになるとさまざまなそばにまつわる文化・習慣が誕生し、今に引き継がれています。その1つがそばをいただく前に軽くお酒を楽しむ食習慣の「そば前」です。
江戸末期の本『江戸自慢』にも、「必ずそば屋には酒あり。しかも上酒なり」と記されています。江戸っ子の間で「そば前」は通・粋な食べ方とされ、おしゃれなそばの楽しみ方としてそばとお酒を楽しむ文化が一気に広まりました。
こちらも合わせてご覧ください。
そばと酒は相性抜群!そば前の歴史やそば屋飲みの作法・お酒の楽しみ方
#3:「みそかそば」「年越しそば」の風習も誕生
現代でも多くの方の大晦日の恒例行事として行っている方が多い「年越しそば」の文化・風習が生まれたのもこの時代です。現在はあまり行われていませんが、「みそかそば」も「年越しそば」と同様に縁起担ぎで毎月末にそばを食べる風習です。
細く長い形状、切れやすさなどのそばの特徴から、厄落としや長寿祈願、家族円満、金運アップなどを願う縁起物として当時は考えられていました。そこから「年越しそば」や「みそかそば」の風習が生まれ、今も続いています。
こちらも合わせてご覧ください。
年越しそばの意味は?いつ食べるのが正しい?由来や歴史、注意点を解説
日本で長い歴史を持つそばを有喜屋でお楽しみください。
有喜屋では、四季折々の風情を感じながらお食事を楽しんでいただけるよう、趣向を凝らしたそば料理を多数ご用意しています。日本で長い歴史を持つそばやそば文化に想いを馳せつつ頂くそばは、さらに味わい深いものとなることでしょう。ぜひ、有喜屋のそばのおいしさを楽しみいただき、ご賞味ください。